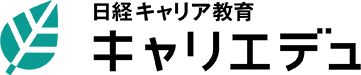文部科学省は、能動的な学習を意味するアクティブ・ラーニングを学習指導要領に取り入れて推奨しています。このアクティブ・ラーニングを実現する教育方法として注目されているのが「問題解決型学習」です。
問題解決型学習は学習指導要領にも言及されている「生きる力」を伸ばす学習方法の一つで、小・中・高校のみならず、大学などの教育現場でも話題になっています。
しかし、よく耳にはするものの、具体的にはどのように実施するのか、どのようなメリットがあるかを知らない人も多いのではないでしょうか。この記事では問題解決型学習を取り入れるメリットと導入事例も併せてご紹介します。
問題解決型学習とは?

はじめに問題解決型学習の概要と、その誕生の背景を解説します。
◇問題解決型学習とは能動的な学習方法
問題解決型学習は、「Problem Based Learning」の頭文字を取ってPBLと略されます。また、「Project Based Learning」と表されたり、「課題解決型学習」と呼ばれたりします。厳密には違いがあるものの同じ意味で使われることも多く、明確に区別する必要はありません。
学生が受け身となってしまう暗記や知識を詰め込むだけの学習ではなく、学生が能動的に問題を発見して解決するのを重視する学習方法を指します。「正しい答えを出すのが重要なのではなく、答えを導き出すまでの過程が大切である」というのがこの学習理論です。
教員は、知識を教える教授者の立場ではなく、助言者として学習者のサポートをします。学生自身の自発性・能動性を引き出し、関心を向けさせるように学習を進めるのが教員の役割です。
初めて教育現場で実践されたのは1900年代初頭。アメリカの教育学者「ジョン・デューイ」が取り入れたとされています。
◇問題解決型学習が注目されるようになった背景
問題解決型学習が注目されるようになった背景には、以下のような事柄が関係しています。
1.AIの発達によるもの
これからの時代、受付や事務作業といった単純業務はAIが代替わりしていくと考えられています。その割合についてはさまざまな意見がありますが、現在ある仕事の半分はAIや機械に替わっていくともいわれます。このような時代を生き抜くために、人間はAIには代替できない能力を身につけなくてはなりません。
AIが代替できない能力の一つは問題解決能力です。社会における複雑な問題解決のためには、思考力・判断力・想像力が必要となります。問題に対して自ら考えて発信する能力や、意見を相手にわかりやすく伝えるための表現力など、AIには取って替わることのできない能力を育むことが非常に重要なのです。
したがって、問題解決型学習は人間ならではの豊かな能力を養うことができる学習方法であるといえます。
2.グローバル化によるもの
グローバル化が進み、多くの国の人たちと関わる機会が増え、ビジネスシーンにおいても海外企業と競い合うことが必要になりました。欧米では、以前からアクティブ・ラーニングが教育に取り入れられています。主体的・対話的な教育が浸透しているため、能動的に動ける人材が多いのが特徴的です。
このような人たちと対等に渡り合っていくためには、問題解決能力の向上が欠かせません。主体的に行動できる人材の育成が求められているのです。今後、ますますAIの発達やグローバル化が進んでいくと考えられます。
さらに、2020年には新型コロナウイルスの感染拡大という新たな社会問題が起こりました。これにより、従来の価値観だけでは通用しなくなる可能性も否めません。初めて遭遇する環境においても問題を解決できる能力が、今後は今まで以上に求められるようになっていくでしょう。
大学で問題解決型学習を取り入れる4つのメリット

問題解決型学習は小・中・高校でも有用な学習方法ですが、ここでは特に大学で活用した場合のメリットを4つ取り上げています。
◇情報リテラシーを身につけることができる
問題解決型学習によって、情報リテラシーを身につけられることが期待できます。情報リテラシーとは、書籍やニュース、テレビ、新聞やインターネットなど、さまざまな媒体から情報収集し、必要なものか・正しいものかを精査して活用する能力のことです。
問題を解決するには、膨大な情報から必要な知識を選択しなければなりません。学習を通して情報収集や情報の取捨選択をするため、自ら集めた情報が正しいか、間違っているかを見極める力が養われ、情報リテラシーを身につけられます。
情報リテラシー教育について詳しくは、下記の記事も参考にしてみてください。
情報(メディア)リテラシー教育とは?必要性や大学における教育方法を解説◇思考力を鍛えることができる
問題解決のためには自分自身で考えて情報を整理することが必要です。正解がない・答えがない問題と向き合うので、従来の教育のように、解き方を覚えて当てはめれば正解が導き出せるわけではありません。そのため学習者自身の思考力が鍛えられます。
実社会においては、正解のある問いはほとんどありません。問題解決型学習では、ある課題をあらゆる視点からとらえ、仮説・検証を繰り返して解決策を導き出す能力が身につきます。考える癖がつくので、日常生活においても物事を深掘りして考えられるようになるでしょう。
◇主体性と協調性を身につけることができる
問題解決型学習は、自分が「問題を解決するために必要だ」と判断したことを中心に学ぶ学習方法です。学習者一人ひとりが自ら考えて問題解決のために行動すると、学んだことが社会でどのように使われるかが実感できます。学びの楽しさ・生かし方を身につけられるので主体的な学びとなります。
従来の学び方は、教科書や参考書と向かい合って一人で黙々とするものでした。問題解決型学習は、チームで協力して一つの問題に取り組みます。互いの意見を聞いたり解決策を議論したりするので、協調性も身につきます。
◇実社会で役立つスキルが身につく
問題解決型学習では、実際に社会で問題になっている課題を取り上げることがあります。ときには企業や自治体と協力して解決する方法も採用されるなど「実践体験型」も珍しくありません。
実際の社会問題に取り組むため、社会との関わり方や実社会で役立つスキルを実践的に学ぶことが可能です。問題解決型学習で身につけた論理的思考力は、ビジネスやコミュニケーションなど、社会に出てからも幅広い場面で活用できるスキルとなります。
問題解決型学習の教育方法
問題解決型学習の教育方法は、チュートリアル型・実践体験型の2つです。どちらの方法においても、次の6つのステップにしたがって進めていきます。
1.テーマ・課題の決定
2.解決策の考案
3.グループディスカッション/調べる対象・課題の明確化
4.自主学習・情報収集
5.得た知識の課題への応用
6.導き出した問題解決策のまとめ・要約
以下では、チュートリアル型・実践体験型それぞれの方法や特徴を見ていきましょう。
◇チュートリアル型
チュートリアル型は、提示された事例や特定の課題に対して、机上でディスカッションやグループワークをする方法です。
学習では、あらかじめ課題が決められていることもあれば、自分たちで課題を見つけ出すところから始めることもあります。事例は、文章や画像、映像などさまざまな形で提示し、課題を決めていきます。
チュートリアル型は、学習が教室内で完結するため、簡単に実施できるのがメリットです。準備の手間もほとんど必要ありません。そのため、大学の授業などで問題解決型学習が実践する場合には、チュートリアル型が多い傾向にあります。
チュートリアル型では、助言するのみの立場である「チューター」という役割が存在し、これを担うのはおもに教員です。チューターは助言するのみであり、学習を進めるのはすべて学生(学習者)となります。
◇実践体験型
実践体験型では、民間企業や地方自治体など実際の現場に入り込み、各所と連携しながら学習します。チュートリアル型と比較して実践的な学習が可能です。実際に起こっている問題・課題に具体的に取り組むため、学習に対しての意欲が高められるのに加え、実際に現場で学ぶことでより高度な知識が身につきます。
学生自身が調べて得た知識は、実際の現場でどのように役立つのかが体験できるため、学習者の記憶に残りやすいというメリットもあります。教室での学習だけでは得られない責任感や統率力など、精神的な学びも多いでしょう。第三者と連携して学ぶことにより、関係性が蓄積され、年々学習環境が整えられていくことも期待できます。
しかしその一方で、実践体験型の学習は綿密な準備が必要です。民間企業や地方自治体との連携が不可欠なため、細やかなスケジュール調整などが欠かせません。学生には、社会で活動するという責任感やある程度の社会常識が求められます。そういった点で、授業として取り入れるにはチュートリアル型よりもハードルが高めです。
大学における問題解決型学習の導入事例を紹介
最後に、各大学の事例をご紹介します。どのように導入されているかを知り、今後の導入の参考にしてみてはいかがでしょうか。
◇千葉大学の事例
千葉大学は、社会環境の向上に貢献する教育を目標とし、問題解決型学習に力を入れています。しかし、これまで紹介したとおり、問題解決型学習には柔軟な学習時間の確保が必要です。そこで、千葉大学では1年間を6タームに分けることにより、学習時間が確保しやすい環境を整備しています。
問題解決型学習を採用しているのは、地域産業イノベーション学やコミュニティ再生ケア学の授業です。地方創生に際して最も大切な要素は「人」です。授業では、「人」の地方回帰を促すために、学年・学部を問わず問題解決に取り組みます。
そのうちの「ローカル・プロジェクト実習」では、空き家をリノベーションして価値を高め、サテライトキャンパスとして再利用するプロジェクトが実施されました。
◇湘南工科大学の事例
湘南工科大学では、各学科で学ぶ専門科目で得た知識や技術を、実際に社会で生かすための学習として多くの問題解決型学習が実践されています。
なかでも特に注目を集めたのは、コラボレーションルームの設置です。コラボレーションルームにはさまざまな情報通信技術を活用しており、情報関連機器メーカーから関心が寄せられました。
問題解決型学習用に5つの教室が新設され、可動式テーブルや椅子、指で書ける電子黒板といった設備がそろっています。これらの設備は、ディスカッションやプレゼンテーションなど、活動形態や授業内容に合わせて自由に構成できます。各自自由学習で得た情報を自由に投写できるといった設備も充実しています。
このような環境整備によって、より多くの情報に触れたり、それぞれの問題解決への活動を広げたりできるので、さらなる学習意欲の向上にもつなげられるのです。
◇多摩美術大学の事例
多摩美術大学が問題解決型学習の科目をカリキュラムに組み入れたのは2006年度からです。さまざまな形で問題解決型学習を取り入れていますが、特に「ARTSAT:衛星芸術プロジェクト」はよく知られています。
「ARTSAT:衛星芸術プロジェクト」は多摩美術大学と東京大学が軸として進めているプロジェクトです。このプロジェクトでは、衛星を専門家だけが取り扱う"特別なもの"から市民にとって"身近なもの"へと意識を変えていきます。目的は、アートとテクノロジーの融合で宇宙を身近に感じさせ、社会に夢と希望を与えることです。
このほか、多摩美術大学では日本赤十字と連携したプロジェクト「日常でいのちの意味を問うプロジェクト」にも取り組んでいます。同プロジェクトは学生たちがアーティストやデザイナーとして問題と向き合い、解決方法を導き出す授業で、美大ならではの取り組みです。
まとめ
問題解決型学習は従来の受け身の学習とは異なり、学生が自ら考え、問題を発見し、解決する能力を身につけるための学習手法です。この学習を通じて学べる主体性や問題解決の能力は、社会人となって仕事や日常生活においても活躍し続けるためには必要不可欠なスキルだといえます。
問題解決型学習の教育方法の一つである実践体験型は、民間企業や地方自治体の協力が不可欠で、スケジュール調整など必要な準備や手間が多いため、いきなり組み込むのには難度が高いでしょう。
一方、チュートリアル型は教室内で完結するため準備も少なく済みますし、実際に多くの大学でも取り入れられています。
しかし、やみくもに問題解決型学習を取り入れても、大きな効果は期待できません。まずは現状の学生たちに何が足りていないのかを把握することが大切です。
キャリエデュの「社会人基礎力診断」は、学生たちの社会人基礎力を診断することができます。何が足りないか・どのようなスキルを伸ばす必要があるかを把握したうえで提示する課題が選定できるので、より効率的に学習が進められるでしょう。
社会人基礎力診断の申し込み・問い合わせはこちら